世界のどこかで、いつも何かが揺れています。
戦争、経済制裁、貿易摩擦、為替の急変動。
これらはニュースの中では遠い話のように聞こえますが、実際には私たちの生活の根底を動かしています。
とくに飲食業のように「物・人・お金」が同時に動く産業では、世界の不安定さが最も早く肌で感じられるのです。
経済は「つながり」でできている
地政学リスクとは、国と国との関係悪化によって経済の流れが滞ることを指します。
現代の経済は、すべてが国際的に結びついています。
食材、エネルギー、物流、観光――そのどれか一つでも止まれば、全体が連鎖的に揺らぎます。
たとえば、原油価格が上がるとガスや電気代が上昇し、食品加工費や輸送費が上がります。
最終的には、飲食店のメニュー価格にまで影響します。
一見、戦争や外交の話が、数ヶ月後の「ランチの値段」や「原価率」に反映されるのです。
世界が分断されるということ
今、世界は大きく二つの経済圏に分かれつつあります。
アメリカを中心とする自由経済圏と、中国や新興国を中心とした別のネットワークです。
かつては「グローバル化」が進み、どの国とも自由に取引ができる時代でした。
しかし近年は、国家安全保障を理由に貿易が制限され、半導体・エネルギー・食糧などが“武器”になっています。
この「経済の分断」は、企業の判断を難しくしています。
安い仕入れ先を選ぶか、政治的に安定した国から買うか。
コストとリスクのバランスを取ることが、どの産業でも重要なテーマになりました。
飲食業にとっても、食材の原産地や物流経路の見直しが避けられません。
飲食業の現場で起きている変化
地政学リスクが高まると、まず影響を受けるのは物流と原価です。
輸入ワインが遅れ、肉の仕入れ価格が不安定になり、調味料の在庫が読めなくなる。
「これまで通り」が通じなくなる中で、現場は日々柔軟な対応を迫られています。
また、為替の変動も直接的なダメージになります。
円安が進めば、海外食材や備品の価格が上昇し、経費全体を圧迫します。
反対に円高になれば、インバウンド需要が減って観光客の足が遠のきます。
つまり、地政学リスクとは外食産業の“空気”そのものを変える要因なのです。
不安が広がると「支出の質」が変わる
戦争や不況のニュースが続くと、人々は財布のひもを締めます。
しかし、すべての外食が減るわけではありません。
むしろ、安心できる場所や人に対しては、支出が集中します。
「なんとなく落ち着く店」「店主の顔が見える店」「地域に根付いた店」
こうしたお店は、社会が不安定になるほど価値を増します。
人は不安を感じると、“信頼できるコミュニティ”を求めるからです。
飲食店は、その小さな拠点になれる存在です。
経営者にできる備え
- 複数ルートの確保
仕入れや備品を一国依存にせず、国内と海外の複線化を意識します。 - キャッシュの安全性を意識する
金融不安に備えて、預金の分散や短期運転資金の確保を徹底します。 - 顧客層の多様化
インバウンド頼みにならず、地元・常連・法人などバランスの取れた顧客構成を維持します。 - 情報感度を高める
政治や経済の変化を「遠い話」と思わず、ニュースを数字と連動させて読む習慣をつけます。 - ブランドの信頼を積み重ねる
不安な時代こそ、“安心の象徴”になるお店が強いです。
価格よりも「この店なら大丈夫」と思ってもらうことが最大のリスク対策になります。
世界が揺れても、人の温度は変わらない
地政学リスクとは、人間の不安が形になったものです。
しかし同時に、人のつながりを見直すきっかけにもなります。
どんな時代でも、人は誰かと食卓を囲み、語り、笑い、明日を考えます。
それが「文明の持続性」そのものです。
もし世界が分断しても、心までは分断されません。
飲食業は、その人と人のつながりを守る最後の場所です。
だからこそ、経済が冷えても、私たちは火を絶やさずに続ける。
それが、世界が揺れる時代における飲食人の使命だと思います。

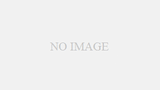
コメント