経済は常に波を描きます。
景気が上がり、人々の気持ちが明るくなり、そしてどこかで行き過ぎて崩れる。
この「行き過ぎと崩壊」を繰り返す現象を、私たちは“バブル”と呼びます。
バブルは突発的な災害ではなく、人間の心理から自然に生まれるものです。
そしてその影響は、金融市場だけでなく、飲食業のような実体経済にも確実に波及していきます。
バブルの始まりは「希望」から
どんなバブルも、最初は“夢”から始まります。
17世紀のチューリップバブル、18世紀の南海泡沫事件、1980年代の日本の不動産バブル、そして2000年代のITバブル。
そのどれもが、「新しい価値が経済を変える」という信念からスタートしました。
人間は未来に期待すると、理性よりも感情が先に動きます。
「自分だけは遅れたくない」という心理が、群衆を同じ方向に走らせます。
それは投資家だけでなく、消費者や企業にも共通しています。
飲食業でも、トレンドが一度火がつくと一気に全国へ広がり、短期間で供給過多になります。
まさに“小さなバブル”です。
群衆心理が市場を動かす
経済学者ケインズは、株式市場を「美人投票」に例えました。
人々は「自分が美しいと思う人」ではなく、「みんなが美しいと思うだろう人」に投票する――。
市場では、実際の価値よりも“他人の期待”が価格を決めます。
つまり、価値とは現実ではなく“集団の幻想”です。
価格が上がるから買う人が増え、買う人が増えるからさらに上がる。
飲食業でも同じ現象が起きます。
SNSで話題になった店に行列ができ、行列があることでさらに人が集まる。
その瞬間、味やサービスよりも「人気」という幻想が人を動かしているのです。
崩壊のきっかけは「安心感」
皮肉なことに、バブルが最も膨らむのは、人々が「もう大丈夫」と思い始めた瞬間です。
過去の暴落も、直前まで楽観論が支配していました。
「まだ上がる」「今度は違う」「市場は成長している」――この言葉が出始めたら危険信号です。
人は群れの中にいると安心します。
多くの人が同じ方向を向いていると、「自分も正しい」と感じます。
しかし、経済には重力があります。
過剰に膨らんだ期待は、必ずどこかで現実に引き戻されるのです。
バブル崩壊と飲食業
バブルの崩壊は、まず「高額消費」から始まります。
高級レストラン、ワイン、高級食材を扱う業態が先に冷え込みます。
次に、接待や出張などの法人需要が落ち込み、やがて日常の外食にも影響が広がります。
1980年代のバブル崩壊後、日本中のレストランが「原価の見直し」と「単価調整」を迫られました。
そしてコロナ後やインフレ局面でも同様の流れが起こっています。
市場が縮むとき、最初に問われるのは“価格の妥当性”ではなく“価値の信頼性”です。
お客様が「なぜこの価格なのか」を納得できる店は残り、
「なんとなく高い」「雰囲気だけの高級感」と思われた店は離れられていきます。
群衆の熱狂に飲み込まれない
経営者にとって最も大切なのは、“群衆の熱狂に飲み込まれない”ことです。
トレンドが広がっているときほど冷静に、売上が伸びているときほど慎重に。
経済全体が浮かれている時期は、原価や人件費、契約条件を見直す好機でもあります。
逆に、世の中が悲観に包まれている時期ほど、チャンスが眠っています。
周囲が投資を止めたときにこそ、良い立地が空き、優秀な人材が動きます。
バブルの裏側には、必ず“再生の扉”が隠れているのです。
バブルの本質は「信じたい心理」
人間は希望を持たずには生きられません。
だからこそ、どんなに痛い目を見ても再びバブルを作ります。
それは愚かではなく、むしろ人間らしさの証でもあります。
しかし、希望には方向性があります。
数字や流行に向く希望は短命ですが、「人の信頼」に向けた希望は長く続きます。
飲食店で言えば、「あの店主に会いたい」「あの空間に癒されたい」という気持ちです。
経済がどんな波を描いても、そうした“人の感情”を中心にした価値は崩れません。
結論 ― 幻想の中でも現実を見つめる
市場はこれからもバブルを繰り返します。
AIが進化しても、データが精密になっても、人間が群れる限りそれは避けられません。
ですが、私たちはその中で生き方を選ぶことができます。
経営とは、幻想に流されず、現実の人間を見続ける行為です。
経済が熱狂しても冷静に、冷え込んでも笑顔を忘れない。
それが、飲食業という“人を中心にした経済”を守る唯一の方法だと思います。

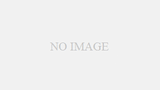
コメント