人間は、失敗の原因を理解していても、何度も同じ間違いを繰り返します。
投資の世界では特にその傾向が顕著です。
リーマンショックでも、ITバブルでも、そして仮想通貨の暴落でも、
多くの人が「今回は違う」と信じて資金を投じました。
人はなぜ、自分だけはうまくいくと思ってしまうのでしょうか。
そしてこの“希望バイアス”は、実は投資家だけでなく、
私たちの生活や飲食業の現場にも深く関係しているのです。
希望バイアス ― 「自分は大丈夫」という錯覚
希望バイアスとは、良い結果が自分に起こる確率を過大に見積もり、
悪い結果は「他人ごと」だと感じてしまう心理のことです。
たとえば「自分は病気にならない」「事故には遭わない」「事業はうまくいく」。
根拠がなくても、私たちはそう思い込みます。
この心理は日常では前向きな力になりますが、経済や経営の判断では危険です。
投資家が「自分だけは売り抜けられる」と信じるとき、
経営者が「この流行はうちだけ続く」と考えるとき、
すでにバイアスの罠にかかっています。
成功体験が作る「過信の連鎖」
人は成功を重ねるほど、冷静さを失いやすくなります。
うまくいった経験が「自分の判断は正しい」という錯覚を強化するからです。
これを心理学では「確証バイアス」と呼びます。
投資の世界では、株価が上がっているときにリスクを無視しがちです。
飲食業でも、繁忙期やブームのときほど経営判断が甘くなります。
「今は勢いがあるから大丈夫」「多少コストが上がっても売上でカバーできる」。
その安心感が、やがて経営の綻びを生みます。
過信は静かに蓄積し、危機の前にピークを迎えます。
そして市場も企業も、人も、そこから学ぶことでしか冷静さを取り戻せません。
群衆の中で失われる判断力
人間は本質的に“社会的動物”です。
周りが同じ行動を取っていると、自分の判断も正しいと思い込む傾向があります。
これを「同調バイアス」と言います。
投資では、他の投資家が買っているから自分も買う。
飲食業では、周囲の店が値上げしているから自分も上げる。
流行に合わせることは悪いことではありませんが、
根拠が「他人がやっているから」になった瞬間、それは思考停止です。
本来、経営判断とは「市場を読むこと」ではなく「自分の店を読むこと」です。
他店の行動より、自分の顧客の声に耳を傾けるほうが正確な情報です。
群衆心理に流されない経営者こそが、危機に強いのです。
飲食業に潜む「希望バイアス」
飲食店経営にも、希望バイアスは数多く存在します。
「この立地なら必ずうまくいく」「このメニューは流行るはず」「スタッフは辞めない」。
しかし、現実は予想通りには進みません。
お客様の嗜好は常に変化し、社会の空気も動きます。
だからこそ、希望ではなくデータと現場の声に耳を傾ける必要があります。
それでも、数字だけでは見えない“感情の変化”を読むことも重要です。
「常連客の笑顔が減っている」「スタッフの表情が硬い」。
こうした小さな兆しこそ、経営の方向を修正するサインです。
希望と冷静さのバランス
経済も商売も、希望がなければ続きません。
未来を信じる力は、人間にとって不可欠です。
しかし希望だけに頼ると、現実を見失います。
大切なのは、「希望を持ちつつ、現実を直視する」ことです。
飲食業で言えば、「売上が伸びる」と信じることと同時に、
「下がったときにどう対応するか」を常に考えることです。
希望とは、備えとセットで初めて価値を持ちます。
冷静さを取り戻すための三つの視点
- 時間をおいて考える
大きな決断ほど一晩寝かせましょう。感情の熱が冷めたとき、見えるものがあります。 - 第三者の意見を聞く
他人の視点は、自分のバイアスを浮き彫りにします。信頼できる仲間の助言を大切に。 - 数字と感情を両方見る
売上データだけでなく、お客様やスタッフの感情の動きも観察しましょう。数字と気配を一致させる意識が重要です。
結論 ― 希望を捨てずに、過信を手放す
投資家が間違えるのは、欲ではなく“確信”のせいです。
「きっと大丈夫」という思い込みが、最大のリスクを生みます。
しかし、希望そのものは悪ではありません。
希望を持つからこそ、人は努力し、挑戦できます。
飲食業も同じです。
ブームやトレンドに惑わされず、自分の信念を冷静に磨き続ける。
その姿勢こそが、長く愛される店をつくります。
経済は波のように揺れ、バイアスは誰にでも生まれます。
だからこそ、私たちはその波を恐れるのではなく、
正直に観察し、静かに舵を切る力を磨く必要があります。
“希望を失わずに、過信を手放す”――。
それが、経営にも人生にも通じる、もっとも現実的なリスク回避策ではないでしょうか。

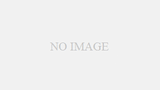
コメント